北海道はもともとアイヌ民族が暮らしていたため、市町村名はアイヌ語に由来している名前が多数を占めます。アイヌ語地名は、自然に寄り添った立場でつけた地名が多く、そのためアイヌ語地名からその土地の昔の姿を想像することが出来ます。しかし、アイヌ語については解釈が難しく、地名についても諸説あるものが多く存在しています。その中で、ここでは各市町村の見解を尊重し、各市町村公式サイトから引用するようにしています。市町村の公式サイト内にある概要や、資料のPDFなどもチェックしました。また、市町村の公式サイトに見当たらない場合は、個人的見解も含めながら探っています。引用元に関しては()にて表示しています。
胆振総合振興局
「日本書紀」によれば斉明天皇の代、阿部臣が北征した時に、胆振金且(いぶりさへ)の蝦夷を宴会に招待したという。 古く新井白石が胆振金且とは北海道の勇払(いぶつ)地域のことではないかと物の本に書いている。 明治初年、松浦武四郎が北海道の国郡名について「噴火湾の山越内から沙流境迄を一国にしたい。その中で、勇払は大場所でアイヌも多いから、中心地としたらよい。」とし、その国名としては「日本書紀の胆振に気が付いたので、胆振でいかがでしょうか。」と北海道開拓使長官に建議した。それで胆振という国名ができた。(胆振総合振興局公式サイト「胆振の概況~胆振(イブリ)という名の由来」より)
この地の中心地とされる勇払はもとは「イブツ」と呼ばれていたそうです。
1869年、開拓使が設置され、蝦夷地を北海道と改称、胆振国には虻田、有珠、室蘭、幌別、白老、勇払、千歳の7郡が置かれ、1879年には室蘭、苫小牧に郡役所が設置されました。1882年に開拓使が廃止されると、函館、札幌、根室の3県が設置され、胆振国は札幌県の管轄となりました。1886年に、3県が廃止され、北海道庁が設置されました。1897年に郡役所が廃止され室蘭支庁が設置され、室蘭、有珠、虻田、幌別、勇払、白老の6郡を管轄することとなりました。1922年室蘭支庁を胆振支庁と改称し、2010年、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例施行により、胆振支庁から胆振総合振興局となりました。
室蘭市
アイヌ語の「モ・ルエラニ」から転化したもので“小さな・下り路”という意味です。崎守町仙海寺(さきもりちょうせんかいじ)前の坂が、ゆかりの地とされています。(室蘭市公式サイト「市の概要~室蘭の語源」より)
1600年ころ松前藩が、アイヌの人たちと交易をするため、絵鞆場所(えともばしょ)を開き、運上屋を置いたのが始まりです。1869年国郡制により、室蘭は室蘭郡に属し、開拓使所管となり、1900年には室蘭郡の9町1村が室蘭町となり、1922年市制施行され、室蘭市となりました。
苫小牧市
以前、苫小牧川が流れる一帯を、当時の河川名であったマコマイ(アイヌ語で「山奥に入っていく川」)と呼んでいた。
沼のあった旧樽前山神社付近一帯はアイヌ語で沼の意味がある「ト」の字をつけて「ト・マコマイ」と呼ばれるようになり、今日の苫小牧になった。(苫小牧市公式サイト「苫小牧市の概要~トマコマイの語源」より)
1869年、蝦夷地が北海道と改められた際、胆振国勇払郡となり、1873年には勇払郡開拓使出張所が苫細(苫小牧)に移転、1874年に苫小牧と改名しました。1902年に2級町村制を施行、1918年には2級町村制のまま町制施行、苫小牧町となりました。翌1919年1 級町村制を施行、1948年に市制施行され苫小牧市となりました。
登別市
アイヌ語「ヌプルペッ」(色の濃い川)(登別市公式サイト「登別市について~基礎データの由来」より)
市内を貫流する登別川のことを指しているようです。
1919年、幌別郡3カ村を大字とし、幌別村となり、1951年の町制施行で幌別町となりました。1961年、町名を登別町に変更、1970年の市制施行により登別市となりました。
伊達市
明治3年(1870年)、亘理(わたり)伊達家の当主伊達邦成(だてくにしげ)とその家来たちが集団で北海道に移り住みました。まだ、人が住めるような土地ではなかった場所を、みんなで力をあわせて畑や道路、家をつくり、村ができました。町の名前は、伊達家の名前をとって「だて」とつけました。これが伊達市の始まりです。(伊達市こどもむけ公式サイト「伊達市の名前の由来や気候など~どうして「伊達市」になったの?」より)
1900年、1級町村制施行により東紋鼈、西紋鼈、稀府、黄金蘂、長流、有珠の6か村を併せて伊達村とし、1925年町制施行により伊達町となりました。1972年の市制施行により伊達市となり、2006年大滝村と飛び地合併で新・伊達市が誕生しました。
豊浦町
地名の由来は、農産物、水産物が豊かで内浦湾に面していることからである。かつては、弁辺(べんべ)と呼ばれていたが、昭和7年豊浦村に改称。弁辺(べんべ)とは、アイヌ語で「ベツベツ(川・川) 小さい川が集まったところ」である。(豊浦町公式サイト「豊浦町概要書~令和2年度(PDF)」より)
「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」によると、べんべという名前はゴロが悪いということで、改名されたとなっています。上述の通り、農産物、水産物が豊かで内浦湾に面していることから名付けられたとありますが、併せて、末永く豊かであってほしいという願いも含まれているようです。
1880年、虻田郡各村戸長役場がおかれ、その管轄下となった年が豊浦町の開基の年とされています。1902年2級町村制を施行し、虻田村に両村組合役場がおかれました。1909年、組合役場を解き字弁辺に弁辺村役場を開設、1932年村名弁辺村を豊浦村と改称、1947年の町制施行により豊浦町となりました。
洞爺湖町
虻田町と洞爺村の町村合併を機に、全国的にも知名度のある「洞爺湖」にちなんで名付けられた。洞爺(トウヤ)はアイヌ 語の「トヤ」が語源で、「湖水に面する肥沃な丘」を意味している。(胆振総合振興局公式サイト「胆振の概況2024~いぶりの11市町紹介(PDF)」より)
1880年虻田村に虻田郡各村戸長役場を設置、1902年に2級町村制施行されますが、1920年、虻田村から洞爺村が分村しました。1938年、虻田村は町制を施行し、虻田町となり、2006年再び虻田町と洞爺村が合併し洞爺湖町となりました。
壮瞥町
アイヌ語で「滝の川」を意味する「ソーペツ」より転化し「壮瞥」となりました。(壮瞥町公式サイト「町の概要~町名の由来」より)
1879年、岩手県人の移住により開拓がはじまりました。1899年、壮瞥村戸長役場が設置され、1915年2級町村制が施行され、1939年には1級町村制施行、1962年に町村施行し、壮瞥町となりました。
白老町
白老とは、アイヌ語で「虻(あぶ)の多いところ」と言う意味の言葉「シラウオイ」からきたと言われています。(白老町公式サイト「白老町の概要~1 位置・地形・気候」より抜粋)
1855年、仙台藩が白老に陣屋を設置しました。1869年蝦夷地が北海道と改められた際、白老郡が設置され、1880年戸長役場が設置されました。1897年北海道内に支庁が設置された際、白老郡は室蘭支庁に属し、1919年、二級町村制を施行。白老村となりました。1954年に町制施行し、白老町となり、現在に至ります。
安平町
明治33年(1900年)苫小牧から安平村として分村。アイヌ語でアラ・ピラ・ペッ「一面・崖の・川」それが音訳で安平になった。昭和27年(1952年)追分が安平から分村、安平は町名を早来と変えた。時を経て平成19年(2006年)この2つの町が再び合併。町名もかつて使っていた安平町となった。(「北海道 地名の謎と歴史を訪ねて」より)
アイヌ語の「アラ・ビラ・ペッ」(片方に崖のある川)の転訛したものである(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」より)
1894年、早来駅が開業すると、鳥取県人などの入植が相次ぎ1893年に追分駅が開業すると、鉄道関係者などが入植し、人口が急増しました。1901年、苫小牧村から安平村として分村、1952年には安平村から追分村が分村し、安平村は早来町、追分村は追分町となりました。 そして2004年「早来・追分合併協議会」が設置され、2006年に「安平町」として再びひとつの町となりました。
厚真町
アイヌ語の「アットマム」(向こうの湿地帯)から転訛したもの。(胆振総合振興局公式サイト「胆振の概況2024~いぶりの11市町紹介(PDF)」より)
1880年戸長役場が設置され、勇払郡役所の管轄となり、1889年、苫小牧外16カ村戸長役場の管轄区域となりました。1897年に苫小牧戸長役場から分離し、戸長役場が置かれ厚真村ができ、1906年、二級町村制を施行、1915年には 一級町村制を施行し、1960年に町制施行し厚真町となりました。
むかわ町
アイヌ語が語源の「ムッカ・ペッ」(塞がる川)から出たもので、「鵡川」が上げ潮のため砂で河口がふさがれるからである。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」より)
2006年に穂別町と鵡川町が合併し、新町「むかわ町」が誕生しました。
参考文献(Amazon)
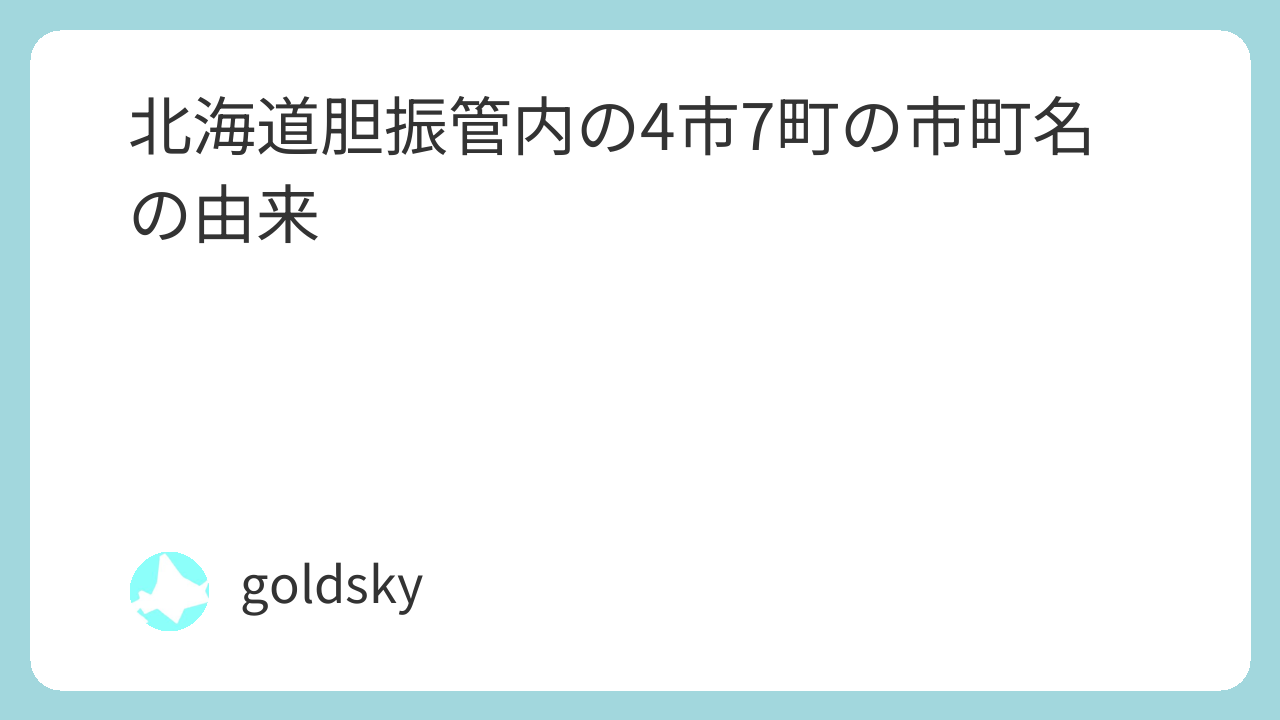
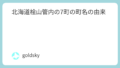

コメント