北海道はもともとアイヌ民族が暮らしていたため、市町村名はアイヌ語に由来している名前が多数を占めます。アイヌ語地名については解釈が難しく、諸説あるものが多く存在しています。その中でも、ここでは各市町村の見解を尊重し、各市町村公式サイトから引用するようにしています。市町村の公式サイト内にある概要や、資料のPDFなどもチェックしました。また、市町村の公式サイトに見当たらない場合は北海道の公式サイトなどを参考に、個人的見解も含めながら探っています。引用元に関しては()にて表示しています。
宗谷総合振興局
宗谷岬の北にある弁天島はアイヌ語で「ソーヤシュマ」と呼ばれていた。また、「岸の海中に岩の多い所」をアイヌ語で 「ソ(ショともいう)・ヤ」と呼んでおり、 これらが「ソーヤ」の由来とされている。(宗谷総合振興局公式サイト「宗谷管内概要~令和6年度 管内概要「宗谷」(PDF)」より)
明治19年、北海道庁が設置され、明治30年には郡役所制度廃止され、宗谷支庁が設置されました。
平成22年、宗谷総合振興局に移行し、同時に幌延町が留萌支庁から宗谷総合振興局に編入されました。
宗谷地方は日本最北の地で、それをうかがわせる碑が多く存在します。
稚内市
アイヌ語の『ヤム・ワッカ・ナイ』 (冷たい水の出る沢)が語源(稚内市公式サイト「稚内市のご紹介」より)
江戸時代、宗谷に藩主直轄の宗谷場所を開設しているので、古くから国の要所となっていたのでしょう。
猿払村
猿払(サルフツ)の語源はアイヌ語の「サロプト」「サラブツ」から転化したもので『葦(芦)川口』『葦(芦)原の河口』を意味しています。(猿払村公式サイト「地名の由来と歴史」より)
猿払の歴史の紹介の中に”「蝦夷日記」に、藤右衛門が宗谷の前浜にソウヤをはじめ、トンベツ、トママエまでの役付や主だったアイヌを集め大酒宴を開いたが、この席にサルフツから嶋綿入りを着た「トンハライ」なるアイヌが招かれたと書き残されています。”とありますが、「トンハライ」という方が気になります。”役付や主だったアイヌを集め”となっているので、猿払のリーダー的な存在だったのでしょう。
浜頓別町
町名は、アイヌ語の「ト・ウン・ペツ」(沼に行く川)を語源に転訛したと解釈されています。
(浜頓別町公式サイト「第6次浜頓別町まちづくり総合計画(浜頓別町の概要PDF)」より)
1878年、枝幸郡に枝幸、頓別、歌登、礼文の 4 ヶ村が設けられ、これが浜頓別町の開基となっているようです。1909年、2級町村制施行により、頓別、歌登、礼文、枝幸が枝幸村に併合されましたが、1916年枝幸村より分村し、2 級町村制を施行、「頓別村」となりました。1951年、町制を施行し、頓別村を浜頓別町と改め現在に至ります。
頓別村になぜ浜をつけたのかは不明です。
中頓別町
「頓別」が頓別川流域を表す大地名となったのちの1916年(大正5年)に、枝幸村(→枝幸町)から頓別川流域を分村するにあたって頓別村と命名された。
その後、1921年(大正10年)に頓別川上・中流域をさらに分村するにあたって、新しい村の中心となったのがすでに中頓別駅が設置されていた(1916年開業)中頓別市街であったことから「中頓別村」と命名された。(Wikipediaより)
中頓別町公式サイトでは町名については見つけることができませんでした。頓別については浜頓別町と由来は同じでしょう。それに頓別川中流域にある地域から中頓別となったようです。
枝幸町
アイヌ語の「エサウシ」より転訛したもので、岬の意があります。また、頭を浜に出していることから名づけられたものです。(枝幸町公式サイト「枝幸町勢要覧(PDF)」より)
北海道には同じ発音の市町村がいくつかあり、「えさし」も枝幸と江差があります。こちらは北見枝幸と呼ぶ人が多いようです。ちなみに私は幸せの枝幸と呼んでいます。
豊富町
町名は、「魚(食べ物)が豊富な川」という意味のアイヌ語の「エベコロベツ」と言う町内の地名に由来します。そこから転じて、石炭、石油、天然ガス、温泉、泥炭等天然資源に恵まれた土地であったことから「豊富(ほうふ→とよとみ)」となりました。(豊富町公式サイト「ふるさと名物宣言 ヘルスツーリズムタウン豊富(PDF)」より)
エベコロベツ川という川は地図では見つけられませんでしたが、下エベコロベツ川は豊富町にありました。ずっと追っていくとペンケ沼から始まっている気がしましたが、定かではありません。
礼文町
礼文島はアイヌ語「レプンシリ」に由来し、「沖の島」という意味で隣接する利尻島とは、輪郭はもとより、地形、地質、さらに生成時期などにおいて、まったく趣が異なっています。(礼文町公式サイト「礼文町の概要(地形)」より引用)
ここでは少し歩いただけで高山植物にであうことができます。礼文島は別名「花の浮島」とも呼ばれています。
利尻町
町名の「利尻」はアイヌ語「リイ・シリ」で「高い・島」を意味します。利尻島の中央に1,721mの利尻山がそびえ立つことから、「高い山のある島」と訳せます。(利尻町公式サイト「町の概要」より)
海を挟んで向こうに見える利尻富士は堂々としていてすがすがしさを感じます。
利尻富士町
利尻島の名称は、アイヌ語で高い島を意味する「リイシリ」に由来する。(利尻富士町公式サイト「町政執行方針」より)
由来は利尻町と同じです。利尻富士町は1990年に町名変更されるまで「東利尻町」でした。利尻島では利尻山の存在が大きいのですが、私の周りでも利尻山というより利尻富士と呼ぶ人の方が多い気がします。
幌延町
幌延とは、アイヌ語の「ポロ」「ヌプ」が転化したもので、『大平原』を意味しており、広大な原野と山林を有しております。(幌延町公式サイト「幌延のプロフィール」より)
大平原とはサロベツ原野ですね。納得です。
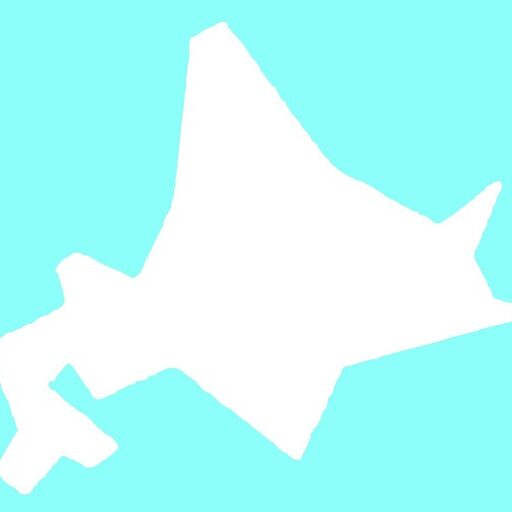
コメント