北海道はもともとアイヌ民族が暮らしていました。現在ではアイヌ民族の伝統的な生活様式をそのまま続けている人はいませんが、北海道の市町村名にはアイヌ語に由来している名前が数多くあり、その地名から、アイヌ文化を感じることが出来るのではないでしょうか。アイヌ語地名については解釈が難しく、諸説あるものが多く存在しています。その中でも、ここでは各市町村の見解を尊重し、各市町村公式サイトから引用するようにしています。市町村の公式サイト内にある概要や、資料のPDFなどもチェックしました。また、市町村の公式サイトに見当たらない場合は、ほかのサイトや、最後に紹介している参考文献から、個人的見解も含めながら探っています。引用元に関しては()にて表示しています。
桧山振興局
「檜山」という地名は、現在の檜山地方南部に自生していたヒノキアスナロの材質が「ヒノキ」に似ていることから、生育している山を檜木山(ひのきやま)と呼んでいたことに由来するといわれています。(北海道教育委員会公式サイト「桧山のあらまし~沿革より抜粋」より引用)
檜山地域は、北海道の中でも古い歴史のある地域となっています。1678年、上ノ国にあった檜山奉行所を江差に移し、ヒノキアスナロ(ヒバ)の伐採と植林事業を実施したのが管内の公的機関設置の始まりとなっています。1897年、道庁官制改正に郡役所が廃止され、江差に檜山支庁が設置されました。2010年檜山支庁を檜山振興局に改組、振興局所在地は檜山郡江差町で、管内に『市』を持たない振興局となっています。
江差町
「えさし」という地名の由来は、昆布が獲れるところ、岬が突き出しているところなど諸説はありますが、はっきりとはわかりません。(江差町公式サイト「江差町の位置・沿革・地勢~沿革」より)
アイヌ語の「エサシ」(みさき)から出たものである。昔江差の中心は津花岬付近にあった(北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局 より)
土器や装飾品が発見されるなど、古くから栄えていたことが伺えますが、江差町としての誕生は1900年、1級町村制を施行した年となるのでしょうか。開基年は明らかになっていないようです。
上ノ国町
15世紀ころ、北海道(夷(えぞが)島(しま))南部の日本海側は、上ノ国(かみのくに)、太平洋側は下の国(しものくに)と称されていた。
勝山館を擁し、日本海・北方交易の拠点として栄えたこの地に上ノ国(かみのくに)の名前が残ったことに由来します。(上ノ国町公式サイト「上ノ国町の概要~1 町名の由来」より)
1988年開基800年事業として北海道夜明けの展望塔が建設されました。そうすると1189年源頼朝が居住した年が開基年となるのでしょうか。その後「安藤氏の乱」があり、ここ上ノ国町の名前の由来に深く関わっているようです。「安藤氏の乱」は「蝦夷の乱」、「津軽大乱」、「津軽騒動」とも呼ばれています。「安藤氏の乱」についてここでは割愛しますが、渡島半島は、津軽の安藤氏の支配下にあり、「下之国」(北斗市(旧上磯町)を中心とした地域)、「松前」(松前町を中心とした地域)、「上之国」(上ノ国町を中心とした地域)にそれぞれ守護が置かれていました。この時の「上之国」の名前が上ノ国町の名前の期限のようです。
1879年、上ノ国村内に3戸長役場が置かれ、1902年には二級町村制が施工され上ノ国村とし、1967年に町制施行し上ノ国町となりました。
厚沢部町
地名の由来はアイヌ語であるが、「アッ・サム(楡皮・干す処)」「ハチャム・ベツ(桜鳥・川)」といった諸説がある。(厚沢部町 移住・定住&観光情報 総合サイト「厚沢部町について」より)
1876年に戸長役場が設置され、1906年、二級町村制の施行により厚沢部村とし、1905年に厚沢部町となりました。
乙部町
乙部とは、アイヌ語「オ・ト・ウン・ペ=川口に・沼・ある・もの」から転化したもので、川は現在、姫川と命名されています。(乙部町公式サイト「乙部町のシンボル~町名の由来」より)
1886年、北海道庁函館支庁官下となり、1902年、2級町村制の施行により、村名を「乙部村」としました。乙部町の町制施行は1965年となっていますが、乙部に人が住んだのは、6千年以上も前と推定され、かつては江差に次ぐ街として発展していました。
奥尻町
町名は、アイヌ語の「向こうの島」を意味する「イク・シリ」が由来。(奥尻町公式サイト「奥尻町の沿革と歴史」より抜粋)
多くの貴重な遺跡や遺物から縄文時代早期に人が移り住んでいたと考えられます。1869年に奥尻群となり「釣懸」「赤石」「薬師」「青苗」の4ヵ村を設置、1906年、2級町村制施行さにより4ヵ村を合併し、奥尻村が創立されました。1966年に町制が施工され「奥尻町」となりました。
せたな町
町村合併の際、新町名を公募して「せたな町」となりました。 ※「せたな」の語源はアイヌ語の「セタルシュペナイ(犬の川)が略されて「セタナイ(犬の沢)」となり、それが「セタナ」に転化したといわれている。(せたな町公式サイト「せたな町の概要~町名の由来」より)
「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」によると、瀬棚町を流れる馬場川という2級河川が町の中央を流れていてその上流から、昔犬が泳ぎ出てきたのを見てこの川を「セタ・ルペシペ・ナイ(犬の越える道のある川)」と呼んだと言い伝えられたそうです。また、「セタ・ニウシ・ナイ(サンナシの木のたくさんある沢)」が語源となっているという説もあるようです。
1897年の二級町村制施行により瀬棚村が誕生、1919年瀬棚村で一級町村制が施行され、1921年の町制施行により瀬棚町となりました。2005年に大成町、瀬棚町、北檜山町が合併し、現在のせたな町が誕生しました。
今金町
区画整備により現在の市街地の基礎をつくった今村藤次郎と金森石郎両氏の姓の冠字をとって市街地を「今金」と呼び、昭和22年には自治制施行50周年を迎えたのを機に「今金町」として町制を施行し、先人たちの偉業に敬意を表しています。(今金町公式サイト「今金町の概要~町の概要」より抜粋)
1897年、瀬棚町から分村し、利別村となり、1947年の町制施行により今金町と改称しました。
参考文献(Amazonより)
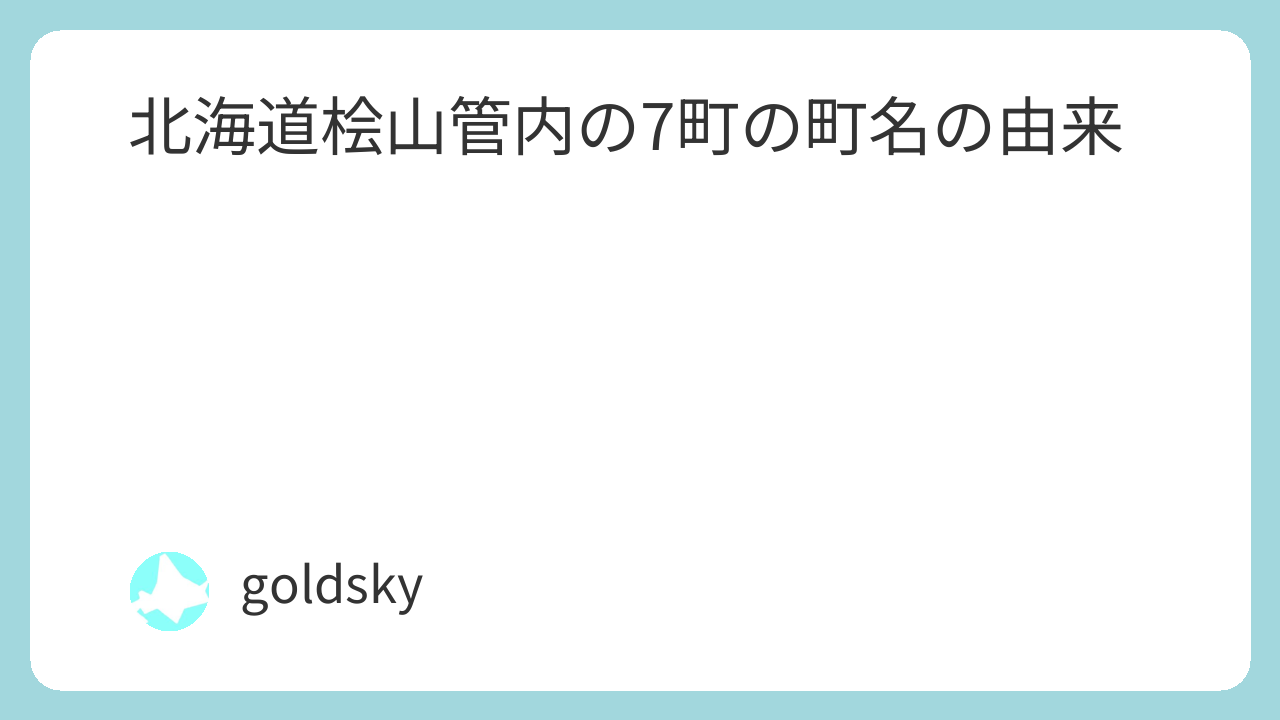
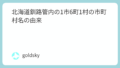
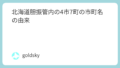
コメント