北海道はもともとアイヌ民族が暮らしていたため、市町村名はアイヌ語に由来している名前が多数を占めます。アイヌ語を日本語に当て字をしたり、アイヌ語の一部を引用して当て字にしたりしているため、意味の解釈が難しく、諸説あるものが多く存在しています。その中でも、ここでは各市町村の見解を尊重し、各市町村公式サイトから引用するようにしています。市町村の公式サイト内にある概要や、資料のPDFなどもチェックしました。また、市町村の公式サイトに見当たらない場合は北海道庁の公式サイトなどを参考に、個人的見解も含めながら探っています。引用元に関しては()にて表示しています。
上川総合振興局
明治2年(1869年)に開拓使判官松浦武四郎が石狩川の神居古潭から上流を石狩国上川郡としたものが現在の地名「上川」の由来となっている。(上川総合振興局公式サイト「かみかわの概要2024」より)
上川総合振興局・地方事務所所在地は旭川市です。上川地域は北海道のほぼ中央に位置し、南北に細長い内陸の地域です。
旭川市
「旭川」と言う自治体名は、市内を流れる忠別川をアイヌが「チュクペッ」と呼んでいると和人が聞き取り、それを「チュプペッ cup-pet :太陽 川(転じて)日が昇る川」と解釈して、1890年(明治23年)に命名されたものである。
「チュクペッ」の音の解釈については、cuk-pet(cuk-cep):秋 川(秋 魚(転じて)鮭)、ciw-pet:波 川とする3つの説がある。(旭川市公式サイト「 アイヌ語地名表示板 「旭川」の命名由来 」より)
旭川市は、道北の要として古くから発展し、現在では北海道で札幌の次に人口の多い都市となっています。この辺りは農業が盛んなため農作物が豊富なのはもちろん、海がないにもかかわらず、道北・道東地域の商業流通の拠点都市となっているため、新鮮な海の幸もそろっています。
士別市
士別市は天塩川流域の市町村の 1 つであり、 アイヌ語で 「本当の川」を意味する 「シペッ 〔si-pet〕」 が町の名前の由来となっています。(士別市公式サイト「士別の歴史(PDF)」より)
士別市の公式サイトで「アイヌ語 由来」で検索すると、上記のPDFが表示されます。天塩川は北海道で2番目に長い川です。
名寄市
地名の「なよろ」が、いつ、どうして使われるようになったのか?これは、100年前の開拓より少し遡らなければならない問題です。・・・(中略)・・・文献と地図にある「ナヨロ」「ナイブツ」は、もともとアイヌの人たちが呼びならわしていたものを、和人が文字に表記したものである。アイヌ語の「ナヨロ」は「ナイ・オロ(川・のところ)」の短縮形で、文献や地図から見ると名寄川そのものを指すようである。名寄川と天塩川の合流点は「ナヨロフト」で、「ナイブト」とも記され、地点を指す。松浦武四郎は「天之穂日誌」では、「此処をナイフトと云うはナヨロフトの詰語なり」と記し、『天塩日誌』で「左ナイブト 本名ナヨロフト」と記している。・・・(後略)(名寄市公式サイト「新名寄市史」より)
名寄市公式サイトに北国博物館販売書籍の紹介の中に「新名寄市史」の紹介があり、紹介ページを開くと上記の文章が掲載されています。抜粋となりますが、名寄市の名寄は名寄川が語源のようで、アイヌ語の「ナイ・オロ(川・のところ)」が由来のようです。
富良野市
アイヌ語の「フラヌイ hura-nu-(臭i ・もつ・所)」が転訛したとする説が有力となっており、富良野川の水源が十勝岳であるために、硫黄の臭気を含むことから呼ばれたと考えられる。(富良野市公式サイト「令和6年度 富良野市の概要(PDF)」より)
十勝岳の硫黄の香りのことらしいですが、実は私硫黄の香りが好きなので、臭いとは思えないんです。
鷹栖町
鷹栖町が未開の地だった頃、トンビをはじめ、ハイタカやオオタカなどの大きな鳥が生息し、大空に輪を描いて舞っていたといわれています。その光景を目の当たりにした人らが「大きな鳥(鷹)の棲むところ(巣)」を意味するアイヌ語「チカップニ」と呼ぶようになったといいます。それが意訳され、「鷹栖」となりました。(鷹栖町公式サイト「鷹栖町について」より)
大きな鳥が悠々と飛んでる光景が浮かんでくるような気がします。このあたりの景色は今も、その姿を彷彿させるような気がします。
東神楽町
神楽村の全域が御料地(皇室の所有地)で、東部に位置することから、「東御料地」と呼ばれていました。1924年(大正13年)、御料地を管理する帝室林野局が借地人に払い下げを決定しました。払い下げにあたり、東御料地を「東神楽」と名付けたことから、地域名として定着しました。1943年(昭和18年)、神楽村から分村の際、地域名をそのまま用いて「東神楽村」と命名しました。
神楽の地名は知里真志保の説によると、アイヌ語地名のヘッチェウシ(hetce-us-i)に由来するとされています。その意味は「囃し・つけている・所」で、いつも歌舞した場所なので、このような地名がつけられたと思われます。それを意訳して「神楽」という地名が生まれました。(東神楽町公式サイト「東神楽町の概要」より)
アイヌ語由来の地名で、自然とは無縁のような語源は珍しく感じます。もしかすると、アイヌ語由来の地名の中で、東神楽は比較的新しい地名なのではないかと思われるのですが。これは私の勝手な想像です。
当麻町
町名は、アイヌ語の「ト」(湖沼)、 「オマ」(に入る)、「ナイ」(川)に由来しています。開拓当初、永山村(現在の旭川市永山地区)に属しており、明治33年の永山から分村時に「當麻」に、昭和33年の町制施行時に「当麻」にそれぞれ改名されています。屯田兵時代に奨励により栽培していた「麻」が非常に良くできる場所だったことから、「麻が当たる場所」としてこの漢字表記が使用されていると言われています。(当麻町公式サイト「当麻町について」より)
アイヌ語由来とも言えますが、この字が使われたことで、日本語由来の地名ともとれるような気がします。
比布町
比布(ぴっぷ)の地名は、アイヌ語のピプまたはピピから出たもので「沼の多いところ」あるいは「石の多いところ」の意といわれています。
昔は湿地帯が多かったことや、石狩川の川床には石が多かったためピプ、ピピが転訛し音訳して名付けられたと考えられています。(比布町公式サイト「まちの概要」より)
比布町では100年も前からイチゴがつくられていたそうです。「ぴっぷいちご」ってひらがなで表記されると可愛らしい名前ですね。
愛別町
町章の説明で「愛別の語源である「矢川」(アイヌ語でアイペット)」となっています(愛別町公式サイト「愛別町のご紹介」より参考)
1988年、町名に「愛」を持つ4つの町(北海道愛別町、神奈川県愛川町、滋賀県愛東町、長崎県愛野町)の間でバレンタインのチョコレートのやりとりや、子ども達の交歓体験交流などの交流がはじまりました。その後、市町村合併によって、愛東町は東近江市に、愛野町は雲仙市に編入され、新たに3つの「愛」のつくまち(愛知県愛西市、滋賀県愛荘町、愛媛県愛南町)が誕生しました。滋賀県愛東町、長崎県愛野町も含めて7つの町の交流は今も続いているそうです。
上川町
今年、上川町はその前身である上川村が愛別村より分村、独立して100 年を迎えました。
1923 年(大正 12 年)に愛別~上川間の鉄道が開通して地域がさらに発展したことで、1924 年(大正 13 年)1 月、愛別村からの分村が実現しました。当時、今の市街地の地域は「留辺志部(ルベシベ)」と呼ばれていたのですが、北見の方にすでに「留辺蘂(ルベシベ)」駅が開駅していたため、諸事情を鑑み、駅名・村名の新名称を皆で話し合ったそうです。「清川村」「川上村」「石上村」「上愛別村」「旭山村」など様々な村名候補があげられましたが、最終的には、石狩川の川上を意味する郷土ということで「上川村」が採択されました。(参考資料:『上川町史』)(層雲峡ビジターセンター公式サイト「センターだより」より)
上川町公式サイトで上川町の名前の由来を探していると、層雲峡ビジターセンターだよりのPDFに上記の記載が見つかりました。そこでビジターセンターの公式サイトを見てみるとセンターだよりのページがあり、その121号「2024年5月24日 UP大雪展望台より上川町市街地と表大雪・北大雪を望む」が見つかりました。その中に上記の文章が記載されています。
東川町
「東川」という地名自体は、文字の見た目の通り、それほど難しい由来ではありません。「なにがしかの川の東…?」と、まあ想像がつきます。単刀直入に言うと、東川=東旭川=旭川の東に位置するまちです。(東川町関連の公式note「「東川」という名前と、アイヌ由来の地名について」より)
東川町関連の公式HP及び、SNSの一覧の中の<SNS一覧>でnote(https://higashikawa-town.note.jp/)があります。note内の記事に「「東川」という名前と、アイヌ由来の地名について」という題名を見つけました。その結果アイヌ語由来の地名の旭川と同じ由来と認識することができるのかな?という結論に達しました。
美瑛町
美瑛町は、十勝アイヌと上川アイヌが狩猟や採集などの食料確保のための往来の際に小屋を建てる等、仮寝の宿を設けていたと言われていますが、アイヌ民族がコタン(集落)を形成して定住した記録はありません。アイヌ民族には道路を造るという習慣はなく、川を舟で移動する、もしくは獣道が利用されていました。そのためか美瑛町には、川に関連したアイヌ語を由来とする地名が多くあります。「美瑛」という地名も、アイヌ語の「ピイェ(油こい川、油ぎった川)」を由来としており、明治 33 年に神楽村から分村した際に村名として名付けられました。美瑛という漢字には、「美しく明朗で王者の如し」という意味が込められています。(美瑛町公式サイト「景観条例・景観計画」より)
景観条例・景観計画のページに美瑛町景観計画の項目の「美瑛町景観計画1(PDF)」を開くと1.美瑛町景観計画策定の背景と目的の(2)歴史〈開拓以前〉に上記の文章が掲載されています。美瑛の美しい自然とそこに住む人たちの力で、美瑛の美しい景観は保たれているんだと感じさせられます。
上富良野町
我が町の地名の由来については、「『かみふらの郷土をさぐる第十四号』平成8年―郷土をさぐる会発行」で詳しく述べたごとく、アイヌ語地名の「フラ・ヌ・イ」の転訛したものに漢字を当てた富良野、更にこの富良野の頭に上の付けたものであるが、改めて簡略に述べてみる。
日本国有鉄道北海道総局「『北海道駅名の起源』昭和48年―改版発行」では、次のように書かれている。
富良野の起源は、アイヌ語の「フラ・ヌ・イ」(においをもつ所)の転訛したもので、富良野川の上流に硫黄山(十勝岳)があって、そこから流れる川水に硫黄の臭気があるため、こう呼んだものである。
上富良野の起源は、富良野川の上流にあるため、(上)をつけたものである。
三人の監修者の一人に、アイヌ語の言語学者である知里真志保氏の名がある。
(上富良野町公式サイト「かみふらのの郷土をさぐる」より)
上富良野公式サイトに「かみふらのの郷土をさぐる」というサイトへのバナーがあり、そこで上富良野の地名について検索をしたところ、15号の中に地名の由来がありました。15号に上記の文章が掲載されていたので、14号もチェックしてみました。すると、上富良野のみならず、いろいろな地名について詳しく掲載されていましたが、ここでは14号の文章の引用とします。
ちなみに「かみふらのの郷土をさぐる」サイトは上富良野や周辺地域、そして北海道の歴史を知りたい方にはお勧めのサイトです。
中富良野町
中富良野町(なかふらのちょう)は、北海道のほぼ中央、富良野盆地にある町。「ラベンダーのまち」として有名です。町名は、アイヌ語の「フーラヌイ」がフラヌイ(臭く匂う泥土・腐れ土)となり、泥炭地帯の中心が本町であることに由来しています。2001年には環境省から「かおり風景100選」に選定されています。中富良野町を含む1市6町村で「富良野・美瑛観光圏」を形成しています。(中富良野町公式サイト「Nakafurano inspires everything ~五感で感じる中富良野~」より)
町政要覧などPDFでも同じような内容の文章が見受けられましたが、観光に関することの中に上記文章発見しました。イギリスとフランスで配信するプロモーション映像の紹介ページの最初にこの文章がありました。アイヌ語の「フーラヌイ」は富良野市・上富良野町・中富良野町・南富良野町すべてに通じていますが、各サイトで少しずつ違う表現になっているのが面白いです。
南富良野町
明治41年に下富良野村戸長役場から分離創設したときに、富良野の南方に位置するところから「南富良野」と名付けられました。富良野という地名は明治19年に内田瀞という人が植民地選定報文に、この地方の原野名を「フラヌ」と仮名書きで記していますが、その後「振縫」という当て字を用いたこともありました。フラヌとは、アイヌ語で「赤色の溶岩や焼け石のたくさんあるところ」という意味で、十勝岳付近の状況を指しています。(富良野町公式サイト「町勢要覧」より)
漢字に関しては初めて知りました。最初は富良野ではなかったのですね。
占冠村
占冠(しむかっぷ)の名前の由来は、アイヌ語の「シモカプ(shimokap)」からで、『とても静かで平和な上流の場所』のことを意味しています。その名の通り今も変わらず、静かで平和な村です。(占冠村公式サイト「占冠村のあらまし」より)
リゾート地として人気の地域。山々に囲まれた自然豊かな場所。上記文章を見て、たしかにその通り。と頷いてしまいました。
和寒町
和寒は昔「輪寒」あるいは「和参」とも書かれ、アイヌ語の「ワットサム」から転訛したもので「ニレの木の傍ら」の意味です。
昔、ニレの木が繁茂していたところから名づけられたものです。(和寒町公式サイト「和寒町の概要」より)
和寒町の町木はニレの木です。
剣淵町
語源は「ケネペツ」。「ケネ」は、はんの木、「ペツ」は川で、「はんの木の多い川」という意味からきている。
また、「ケネペツ」を早くいうとケンプチと聞こえるところからケンブチ(剣淵)と呼ばれるようになった。
(上川振興局の公式サイト「市町村行財政ー行財政概要のぺージ(令和5年度)」より)
剣淵町の公式サイトでは見つけられませんでした。次に上川振興局の公式サイトの行財政概要のぺージ(令和5年度)で、剣淵町のPDFを見たところ上記文章を見つけました。他の年度もチェックしてみたところ「市町村要覧3(PDF)」の内容は毎年変わりはないようです。
剣淵町は現在「絵本の町」として絵本の里づくりに力を入れています。
下川町
ここは名寄川南支流のパンケ(下の)・ヌカナン川と、ペ ンケ(上の)・ヌカナン川が流れている所で、そのパンケ・ヌカナンを意訳して「下川」という名にしたのだという。(北海道公式サイト「アイヌ語地名リスト(PDF)」より)
下川町の公式サイトで見つけることができませんでした。上記文章のほか「一般財団法人 北海道道路管理技術センター」サイトで「北の交差点」という冊子を発行しています。サイトではPDFで記事の内容を見ることができ、バックナンバー4に下川町紹介記事が載っています。そこに町名の由来を「アイヌ語でこの地を指したパンケ(下)ヌカナン(沢・川)を意訳」という下川町情報も載っています。
美深町
現在町名を「びふか」と呼んでいますが、昔は「ピウカ」(アイヌ語で「石の多い場所」)と呼んでいました。 町章は、外側の太い線が男性を、内側の細い線は女性を表し、「ぴうか」の「ぴ」を図案化したものです。町民全体がお互いに手を握り合って、融和団結のもとに明るく住みよい郷土、美深の町の新しい町づくりと町勢の発展を意味して全体の文字を円形にまとめ形象したものです。(美深町公式サイト「美深町章の由来」より)
美深町は天塩川が南北に貫いて走っています。石の多い場所というのも、天塩川の河原のことのようで、天塩川は、美深町の町民憲章冒頭にも出てくる「私たちは、天塩川流域にひろがる沃野と広大な森林に囲まれた美深の町民です。」の言葉通り、美深町にとって唯一無二の存在のようです。
音威子府村
アイヌ語で濁りたる泥川、漂木の堆積する川口、または切れ曲がる川尻の意。
昭和38年常盤村から音威子府村に改称する。(音威子府村公式サイト「村の概要」より)
音威子府村のサイト内で音威子府総合計画を見ると、音威子府村の概況でもう少し詳しく説明があり、”地名が示すとおり「オ・トィネ・プ」はアイヌ語であり、アイヌが先住していたところです。また、「北海道命名の地」としての歴史も有しています。”という文言が見つかりました。この「オ・トィネ・プ」について調べてみると、紋別に同じアイヌ語由来の灯台がありました。音稲府岬灯台(オトイネップは「オ(川口)・トイネ(濁っている)・プ(者:川)」の意味。)という発音は同じでもそれに宛てた漢字が違います。
アイヌ語由来の地名を調べてみると、全く違う場所で同じ地名がいくつもあるんです。「~コタン」とか「ペンケパンケ」など。こうして由来を調べていると、「あ、さっきも出てきた」ということがしょっちゅうで、なかなか前に進めません。
中川町
当地は入植当初は無名村であったため、所属郡名である中川郡から命名された。(Wikipediaより)
中川町公式サイトでは地名の由来について見つけられませんでしたが、歴史を見てみると、中川村の名前が使われたのは1906年。その後1919年二級町村制が施行され「中川村役場」が設置され、現在に至っているようです。Wikipediaなど調べてみましたが、中川は天塩川の中流の意味で、アイヌ語とは関係ないようです。
幌加内町
ほろかないの由来は、「逆戻りする川」という意味があり、町の南部を流れる幌加内川を指した、アイヌ語の 「horka-nay ホロカナイ」の意とされています。(幌加内町公式サイト「町の概要」より)
幌加内川は雨竜川の支流で、その雨竜川は石狩川の支流です。
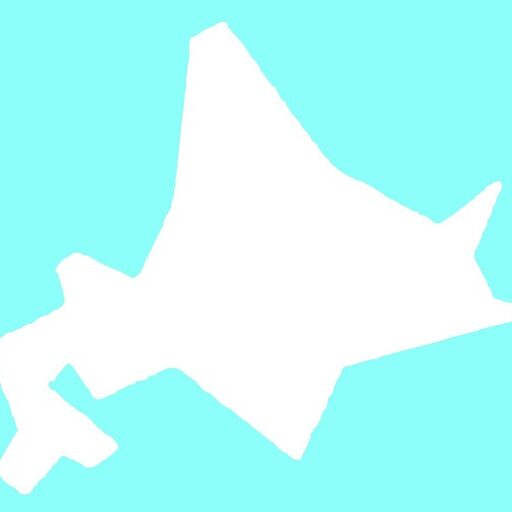
コメント