北海道はもともとアイヌ民族が暮らしていたため、市町村名はアイヌ語に由来しているところが多数を占めます。アイヌ語地名については解釈が難しく、諸説あるものも多く存在します。その中でも、ここでは各市町村の見解を尊重し、各市町村公式サイトから引用しています。市町村の公式サイト内にある概要や、資料のPDFなどもチェックしています。市町村の公式サイトで見当たらない場合は、ほかのサイトや書籍などの引用により、個人的見解も含めながら探っています。引用元に関しては()にて表示しています。
渡島総合振興局
道南の地には古くから倭人が渡って来ていましたが、鎌倉時代から南北朝、室町時代になると、戦乱や飢饉などから逃れて渡来するものが多くなり、また、奥羽、北陸地方の漁民などに未開の新地として注目されるようになりました。これらの人々を当時、渡り党(島)と称し、渡島(おしま)の名もそこから始まったと言われます。明治2年、松浦武四郎は北海道の国郡名の案を考えて建議書を提出し、同年の11国86郡設置のおり、当地は「渡島国」と名づけられました。(渡島総合振興局公式サイト「渡島の現況~【目次】(PDF)」より)
北海道南端地方に当たるとの見解からこの地を選び対岸の南部津軽の人がこの地を指して「おしま」と呼んでいたのでこの呼び方に従ったものである。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」より)
開拓使設置前の北海道は蝦夷地と呼ばれ、江戸時代には、松前藩(現在の北海道松前郡松前町)がその一部を支配していました。1869年、蝦夷地が「北海道」と改称され、開拓使が設置されると、1872年には札幌開拓使庁が本庁となり、函館出張所は五支庁のうち一つの函館支庁となり、この直後に旧松前藩領地が函館支庁の所管となり、渡島七郡と胆振八郡が所管地となりました。1882年に開拓使が廃止された後には根室県、札幌県とともに函館県が置かれ、1886年には北海道庁が設置され、その下に函館支庁、根室支庁が置かれましたがすぐに両支庁は廃止され、業務は道庁と郡役所に分割されました。ただし函館には外交上の配慮から外国人に関する事務を担当する北海道庁長官出張所が1890年まで置かれ、1897年に郡区役所に代わる形で函館支庁が復活しました。ただ、函館支庁は函館区のみが管轄区域で、渡島には他に亀田支庁、松前支庁、檜山支庁が置かれていました。1899年、亀田支庁と函館支庁が統合され、函館支庁に改称。1903年、松前支庁が函館支庁に統合され1922年、渡島支庁に改称されました。2010年、渡島支庁は渡島総合振興局となり、現在に至ります。
函館市
室町時代の享徳3年(1454年),津軽の豪族 河野政通が宇須岸(ウスケシ:アイヌ語で湾の端の意)と呼ばれていた漁村に館を築き,この館が箱に似ているところから「箱館」と呼ばれることになりました。この館跡は今の基坂を登ったところです。明治2年(1869年),蝦夷が北海道となり,箱館も函館と改められました。(函館市公式サイト「函館市の概要~地名の由来」より)
津軽の河野政通がこの地に城を築きその形が箱のようであったので人々はこれを箱館と呼んだのが地名の起こりとなり、明治2年、開拓出張所設置の際に「函館」と改められた。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」より)
函館の地名の由来で”河野政通が漁村に館を築いた”のは1454年。その後、この地はアイヌの攻略により和人は亀田に移り、再びこの地が栄え始めたのは江戸時代になってからです。1859年、箱館港は、横浜・長崎とともに日本最初の国際貿易港と開港しました。1868年、明治政府が箱館裁判所を設置、1か月後に箱館府と改称されるも、1869年には箱館府を廃止し開拓使出張所が置かれました。1879年、郡区町村編制法施行により「函館区」が設置され、1922年、函館区が市制施行し函館市となりました。
北斗市
合併協議会で一般公募し、1308点応募があり合併新市名選考小委員会を開催し検討の結果6点まで選考し、この結果をもとに合併協議会委員25人の投票により決定しました。
応募者からは「北の空(大地)」にさんぜんと光り輝く星(街)(北斗星)。他の市町村の範となると同時に、個性を失わず独自の輝きをもつ街づくり」との思いが含まれており、「北斗とは小さな星がかたまりあって一つの核をなすともいわれており、上磯町と大野町の輝かしい二つの星が一つの北斗をつくり上げ、これから立派なまちづくりを進めていこう」という願いが込められています。(北斗市公式サイト「北斗市の概要~市名」より)
旧上磯町は、1880年に上磯村ほか4か村戸長役場が設置され自治制を施行、1918年に町制を施行しました。旧大野町は、1880年に大野村ほか5か村戸長役場が設置され、1900年に大野村に、1957年に町制を施行しました。2006年、旧上磯町と旧大野町が合併し、北斗市が誕生しました。
松前町
「万堂宇満伊犬(まどうまいぬ)」という地名、アイヌ語の「マツ・オマイ」「マト・マイ」(婦人の居るところ)というところから、先住民の住む地(蝦夷)に和人の女性も住むという珍しさを表しているといわれています。(松前町公式サイト「松前町の概要~町名の由来」より)
付近は鎌倉時代末期より本州から北海道に移住した人たちの根拠地の一つで、1514年、蠣崎氏が本州から北海道に移住する人を統一、松前藩の基を築きました。この松前という名前は蠣崎氏が改めた姓で、当時豊臣秀吉の重臣であった松平家康と、前田利家の両社の姓を一字ずつとったものと言われ、また、城下の海に面して大きな松があり、これを目当てに船が出入りしたので松前に至ったともいわれるそうです。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」参考)
松前町は、江戸時代に最北の城下町として栄えました。1900年、松前町の前身である福山町が発足しました。1940年、福山町が改称して松前町となりました。
福島町
寛永元年(一六二四)月崎神社の御神託により、藩に願い出て福島村と改村したといわれている。この福島の地名については、現在の松前町の城跡地域を古くは福山と呼んでおり、それに対する福島なのか、本州対岸の青森県内の福島の地名を吉祥字として吸収して地名としたのかは定かではない。(福島町公式サイト「福島町史 通説編~福島町の地名」より抜粋)
福島町の開基は、1189年源頼朝の奥州征伐の際、破れた奥州藤原の残党が津軽から逃げ渡り吉岡村に定住したのが始まりとされています。福島村の沿革については明確な記録はありませんが、福島町史で幕末時代になってからの記録が紹介されています。「福島町の文化財」の福島町の歴史を知るりすとで読むことが出来ます。
知内町
アイヌ語の「チリ・オチ」(鳥いるところ)の意味があります。知内は鷹の産地として有名で、松前藩が徳川将軍家に鷹狩り用に献上する15羽の鷹のうち、半数以上は知内で捕獲したものと言われています。(知内町公式サイト「町名の由来」より)
知内には古くから人が住んでいたようで、多くの遺跡が発見されていることでもわかります。その中には旧石器時代の石器も発見されています。
1886年、道の区域を管轄する北海道庁が置かれると、1888年に知内村ほか1村戸長役場が設置され、1906年、二級町村制により、上磯郡知内村となり、1967年町制施行により知内町となりました。
木古内町
木古内の地名は、アイヌ語の「リコナイ(高く昇る源)」、または「リロナイ(潮の差し入る川)」から転訛したものと言われています。(木古内町公式サイト「町の概要~町名」より)
現在の木古内川をむかし、アイヌ語で「リロナイ」といい、これが「きこない」に転かしたものであると言われている。「リロナイ」とは「リリ・オ・ナイ」(海水の差し入る川)いう意でこの沿岸は干満の差が大きく、満潮時には海水が逆流するのでこう名付けられたという。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」参考)
木古内(きこない). 「きこない」といわれるようになったのは、1624年に松前藩が領内を巡行したときに付けられたのが始めとされ、1879年には3村戸長役場を設置、1902年二級町村制により、上磯郡木古内村となり、1942年の町制施行により木古内町となりました。
七飯町
アイヌ語の「ヌ・アン・ナイ」(漁のある川)から「ナンナイ」となり、それに七飯の字を当てた。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」参考)
七飯町歴史館のサイトでは「ななえの地名」の由来のページがあり、「七重(ななえ)」の説明で
”諸説あるようですが、「ナアナイ」(いくつもの川の意)、「ヌアンナイ」(豊かな沢の意)などのアイヌ語から発祥しているようです。”
となっています。
1869年、蝦夷を北海道と改め、七重は渡島国、亀田郡七重村となりました。1907年に1級町村制を施行、1957年、町制施行し七飯町となりました。
鹿部町
アイヌ語「シケルペ」が町名の由来。「シケルペ」とは「キハダ(一名シコロ)のある所」の意で、イナウ(神祀る木弊)・薬用・染料他に使う貴重な木であるキハダが多い事からそう呼ばれ、後に転訛して「鹿部」となりました。(鹿部町公式サイト「鹿部町の概要~町名の由来」より)
もとアホウドリが多く住んでいたのでアイヌ語の「シカベ」(アホウドリ)から出たものであろう。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」参考)
1879年、戸町役場が開設され、1906年の二級町村制の施行により、茅部郡鹿部村となり、1893年の町制施行により鹿部町となりました。
森町
古くからアイヌ語でオニウシ(樹木の多くある所)と呼ばれていた森町は、漁業の地として知られ江戸時代初期より、箱館周辺の漁民がニシンなどのさかなを求めて出稼ぎに来た所でした。(森町公式サイト「森町のあゆみ」より抜粋)
アイヌ語でオニウシ(樹木の茂った所)と言ったのを意訳して「森」というようになり(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」参考)
1881年、森・尾白内・宿野辺の3村を管轄する森外2ヶ村戸長役場が開庁し、1889年には鷲ノ木・蛯谷・石倉の3村を管轄する鷲ノ木村外2ヶ村戸長役場と合併して森外5ヶ村戸長役場となり、1902年に森村、1907年には一級町村制を施行、1921年には町制が施行されて森町が誕生しました。
八雲町
八雲(やくも)という地名は、八雲地域を開拓した旧尾張藩主・徳川慶勝公が豊かで平和な理想郷建設を願って須佐之男命(すさのおのみこと)が結婚のために新築する家を喜び祝うために歌ったとされる古事記所載の和歌「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣つくる その八重垣を」にちなんで名付けられました。(八雲町公式サイト「八雲町の概要~太平洋と日本海 二つの海をもつまち 八雲町」より抜粋)
1881年八雲村とし、戸長役場が設置されます。八雲村は1902年には北海道二級町村制施行により山越内村と併合、1919年に町制施行され、八雲町が誕生しました。
長万部町
本来はアイヌ語の「オ・シャム・ペッ」(川尻が横になっている川)であったが「シャマンベ」(カレイ)を連想して「オ・シャマンベ」となり、河口付近にカレイの漁が豊富であったためこの名があるという解釈が生じ、また長万部山の残雪がカレイの形に見える頃を漁期としたという伝説もそこから生まれた。(「北海道 駅名の起源 日本国有鉄道北海道総局」参考)
1873年、村の首長が置かれたということで、この年を長万部町の開礎としています。1906年に二級町村制が施行され、1923年には一級町村制が施行されました。1943年の町制施行により、長万部町となりました。
参考文献(Amazonより)
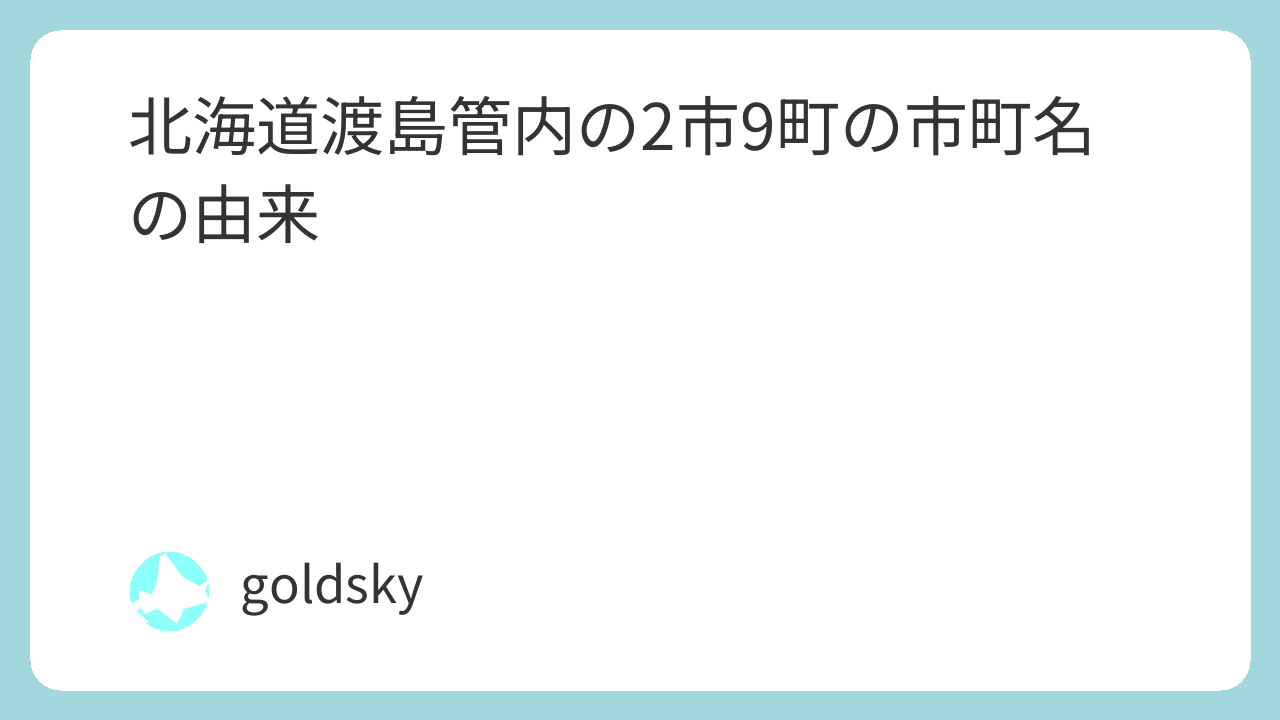
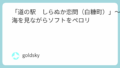

コメント