北海道はもともとアイヌ民族が暮らしていたため、市町村名はアイヌ語に由来している名前が多数を占めます。アイヌ語地名については解釈が難しく、諸説あるものが多く存在しています。その中でも、ここでは各市町村の見解を尊重し、各市町村公式サイトから引用するようにしています。市町村の公式サイト内にある概要や、資料のPDFなどもチェックしました。また、市町村の公式サイトに見当たらない場合は北海道の公式サイトなどを参考に、個人的見解も含めながら探っています。引用元に関しては()にて表示しています。
空知総合振興局
アイヌ語の「ソーラップチ」が語源とされている。「ソー」は滝、「ラップチ」は下るという意味である。それは、原始の森を流れる空知川と石狩川のすさまじくも雄々しい姿をしのばせる。(空知総合振興局公式サイト「空知の概要2024~01 目次 (PDF)」より)
1882年、函館・札幌・根室の3県が置かれた際、空知は札幌県に含まれ、空知郡に市来知村(いちきしりむら)を設置して、空知集治監が設営され、1884年空知郡役所が開庁しました。1886年、3県1局が廃止され、北海道庁が置かれ、1897年道庁が官制を改正し、従来の郡役所を廃止して支庁を設置、空知支庁が誕生しました。2010年北海道空知支庁が廃止され、北海道空知総合振興局が設置されました。
夕張市
アイヌ語のユーパロ(鉱泉の湧き出るところ)の転訛したものといわれています。(北海道夕張市公式サイト「夕張市の概要」より)
夕張にはかつて温泉がいくつかあったように記憶していますが、私の知る限りほとんどが廃業や休業状態。とっても残念。夕張市の公式サイトには「借金時計」があって、夕張市の市債(借金)の残高は確実に減っていってます。元気な夕張が戻ってくる日が近いことを、願っています。
岩見沢市
明治11年に幌内煤田を開採のため、開拓使は札幌~幌内間の道路を開削に当たり、工事に従事する人たちのため、当市の北部、幾春別川の川辺に休泊所を設け、ここで浴(ゆあみ)して疲れをいやしたといわれています。 当時の人々にとって、この地は唯一の憩いの場所として、「浴澤」(ゆあみさわ)と称するようになり、これが転化して「岩見澤」(いわみざわ)と呼ばれるようになったといわれています。(岩見沢市公式サイト「地名の由来」より)
「ゆあみ」について調べてみました。ゆあみの「ゆ」とは、清らかなもの、けがれがないという意味があり、「あみ」は、浴びるという意味(日本浴用剤工業会サイトより引用)だそうです。
美唄市
美唄とはアイヌ語「ピパオイ(沼の貝の産するところ)」からきている。(美唄市公式サイト「美唄市の概要(PDF)」より)
美唄で沼と言えば宮島沼ですかね。マガンの飛来地です。
芦別市
「芦別」の語源には、「ハシュペッ」低木の中を流れる川、「アシペッ」立つ・川の二つがあるといわれています(芦別市公式サイト「芦別市の概要の沿革」より)
芦別川が語源ということですね。芦別川は石狩川の支流です。
赤平市
「赤平」はアイヌ語で「山稜の崖」を意味する「アカピラ」に由来する。(赤平市公式サイト「あかびらくらしのガイド(2014年版 ごみ分別のみ2022年)(PDF)」より)
「ピラ」はアイヌ語で崖を意味するのですね。それに対して「平」の文字を使っているのは何だか違和感が。。。「豊平」や「平取」の平も同じ意味で使われているようです。
三笠市
空知集治監にあった裏山が奈良の三笠山に似ているという、囚人が望郷の念をこめて当時から三笠山と呼んでいました。
明治39年(1906年)、市来知・幌内・幾春別の三村合併のときにこの山の名を取って三笠山村としました。
昭和17年に三笠町が誕生し、昭和32年に三笠市(北海道内で22番目の市)となりました。(三笠市公式サイト「三笠市について」より)
北海道は移住者も多く、故郷への思いが込められた地名も結構あります。ここは、奈良県の三笠山が由来となっているのですね。
滝川市
滝川市の語源は、アイヌ語の「ソーラプチ」=「滝下る所」を意訳したものです。また、空知川の中流には滝のような段差がありアイヌの人々から「ソーラプチペツ」= 「滝のかかる川・滝の川」と呼ばれており、滝川という地名がつけられました。(滝川市公式サイト「滝川市のプロフィール(歴史)」より)
アイヌ語の和訳の方が地名になったようですね。
砂川市
砂川の語源は、アイヌ語のオタ・ウシ・ナイを意訳したものです。「オタ」は砂、「ウシ」は多い、「ナイ」は川を意味しています。石狩川と空知川に抱かれるような地形の砂川には、上流に歌志内を源とする「ペンケオタウシナイ川」と、下流に市街の中央を流れる「パンケオタウシナイ川」があり、アイヌ語の地名「オタウシナイ」が生まれたものと考えられています。(砂川市公式サイト「プロフィール」より)
空知地方には和訳の方が地名になっているところが多いような気がします。
歌志内市
市内を西に向かって二分して流れる「ペンケウタシュナイ川」の名に由来しており、アイヌ語で、「砂のたくさんある沢」という意味です。明治24年に北海道炭砿鉄道株式会社の鉄道開通の際、その意をとって歌志内と称し、これを地名としました。(歌志内市公式サイト「地名の由来、市章、歌志内市民憲章、市の花・木・鳥、シンボルキャラクター」より)
砂川が和訳の地名であるのに対し歌志内はアイヌ語がそのまま地名になっているんですね。
歌志内市は炭鉱の閉山とともに過疎化が進み、今は日本一人口の少ない市となっています。
深川市
深川市史に色々な説が書かれております。その一つとして、深川市街の北側を東西に流れる大鳳
川は、アイヌ語で「深い・川」の意味を持つオオホ・ナイが語源で、これを和訳したという説があります。なお、深川の地名が最初にでてきたのは、 明治 25 年2月4日の北海道庁告示で、そこに深川村という表示がされました。(深川市公式サイト「アイヌ語地名一覧」より)
深川も和訳の地名となっているようです。
南幌町
本町は昭和37年5月1日「幌向村」から「南幌町」と呼び名が改められ、村から町となりました。これに伴い、2年後の昭和39年6月10日、町章が制定されました。この時、南幌町は「みなみほろ」と呼ばれており町章公募も当然「みなみほろ」の図案化でした。応募作品30点の中から「みなみほろ」の5文字をカタカナで円を形どり、町の安定と町民の融和を表し、さらに夕張川・千歳川・旧夕張川の3川に囲まれた、地形を象徴した作品に決まりました。(南幌町公式サイト「町の紹介」より)
幌向は、アイヌ語の「ポロモイ」で、川が大きく曲がっていて水がゆっくり流れているところの意味です。現在は「みなみほろ」から「なんぽろ」と呼び名も変わっています。
奈井江町
奈井江は、アイヌ語の「ナヱ」から転訛したもので「砂多き川」の意味です。(奈井江町公式サイト「町の概要」より)
砂川・歌志内に続きここも「砂」に関連した地名なんですね。石狩川やその支流の空知川そこから枝分かれした川のことでしょうか。
上砂川町
母町である砂川は、アイヌ語で「オタウシナイ」で「オタ」は砂、「ウシ」は多い、「ナイ」は川という意味から砂川と命名され、砂川の上流にあることから「上砂川」と決定し、分町によって「上砂川町」と命名されました。(上砂川町公式サイト「上砂川町の概要」より)
上砂川の上は上流の意味なんですね。北側にあるとか大都市に近い方に上をつけることがあるので、札幌よりだから上砂川となっていると思っていましたが、よくよく見てみると北側でもなければ札幌との距離もはっきりしませんでした。
由仁町
アイヌ語の「ユウンニ」(温泉があるところの意味)がなまったものといわれています。 明治25年、戸長役場がおかれ由仁村が誕生しました。昭和25年、町制施行。平成24年に開町120年を迎えました。(由仁町公式サイト「由仁町の紹介」より)
由仁町の地名の由来を見て「ユンニの湯」を思い浮かべる道民は少なくないでしょう。お勧めです。
長沼町
本町の西1線北15番地付近に、アイヌ語で「タンネト-」という沼がありました。タンネト-とは和名で“細長き沼”という意味で、ここから「長沼」という地名が生まれ、現在はこのタンネト-の碑が残されています。(長沼町公式サイト「長沼町ってどんな町?」より)
長沼のジンギスカン「タンネトウ」はここから名付けられたんですね。美味しいですよ。
栗山町
「栗山」という語源は、アイヌ語の「ヤム・ニ・ウシ」に由来し、「栗の木の繁茂しているところ」に起源しています。
1888年(明治21年)5月16日宮城県角田藩士泉麟太郎氏が「夕張開墾起業組合」を設立7戸24人が阿野呂川右岸(角田)に入植。
1890年(明治23年)には「角田村」設置が告示され、1900年(明治33年)角田村戸長役場が設置されました。
開田事業、二股炭礦開坑、奥地開発、栗山市街地区の商工振興などで、1900年(明治33年)の角田村の戸口が1,200戸、5,000人を突破。
1902年(明治35年)に二級町村制が施行され、自治体としての新生の第1歩を踏み出しました。
二級町村制を5年経験した角田村は、1907年(明治40年)に一級町村に昇格しました。
昭和に入り、角田炭礦の発展とともに人口は20,000人を突破し、1949年(昭和24年)に町制が施行され「栗山町」と改称、1963年(昭和38年)には役場庁舎を角田から栗山へ移行しています。(栗山町公式サイト「町名の由来・歴史」より)
栗山町もアイヌ語の和訳が地名になっているんですね。実は栗って寒さに弱いらしく、生産するのは難しいらしいんです。それでも栗山町の地名にもなっている栗ですから、生産者はブランド化を目指して日々試行錯誤しているらしいです。ふるさと納税でも「栗山栗」の取り扱いが始まっています。
月形町
月形町は、内務省御用掛権少書記官から樺戸集治監(明治14年~大正8年)の初代典獄に任ぜられた月形潔氏の姓を取り、明治14年7月1日、空知支庁管内第1号の村として誕生しました。
樺戸集治監は、明治維新後の新政府が全国多数の国事犯や重罪犯を収容するために、全国で3番目、北海道では最初にシベツブト(現在の月形町)に設置されました。
この集治監の囚人による農地開墾や道路開削などが礎となり、今日の月形町があります。(月形町公式サイト「沿革」より)
月形さんという方にはお会いしたことがありません。月形潔氏は地名だけを残し北海道を去っていったので(最後は福岡でした)月形姓は北海道では見受けられないかもしれません。
浦臼町
アイヌ語のウラシナイ(笹川の意)による説、ウライウッナイ(やながついてる川の意)による説があります。
※やな【梁・簗】川の瀬などで魚をとるための仕掛け(国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部「市町村紹介(浦臼町)」より)
アイヌ語由来のようですが、諸説あるようです。浦臼町の公式サイトでは見つけられませんでした。
新十津川町
1889年 明治22年8月 十津川郷大水害にあう
1889年 明治22年10月 第1回北海道移住民出発
1889年 明治22年11月 移住民空知太に到着、 村名を新十津川とする
(新十津川町公式サイト「歴史>あゆみ>明治」より)
新十津川町の公式サイト「新十津川町開町130周年記念映像」のあいさつ文に”本町は母村・奈良県十津川村から移住された先人達が開拓し、令和2年に開町130年を迎えました。”とあります。新十津川の方たちは奈良県十津川村を母村と呼び交流が続いているようです。
妹背牛町
町名の由来はアイヌ語のモセウシでイラクサが繁茂する所という意味。当初は「望畝有志」と表記していていたが、1898年(明治31年)に「妹背牛」に表記が変更され、ほぼ同時に「妹背牛駅」が開業した。(妹背牛町公式サイト「移住情報 妹背牛町×HO特別編集企画パンフレット(PDF)」より)
今の表記でも難読ですが、当初はもっと難読だったんですね。妹背牛駅は無人駅となりましたが、現在も稼働しています。
秩父別町
秩父別の名は、アイヌ語の「チックシベツ」に由来し、「通路のある川」を意味しています。(秩父別町公式サイト「秩父別の概要」より)
通路のある川とは川が通路になっているのでしょうか。Wikipediaによると舟・通る・川という意味もあるようなのでこの川を道のように舟で利用してたということかもしれません。
雨竜町
雨竜(うりゅう)とは、アイヌ語の地名「ウリロペツ」(鵜の多い川という意味)より転訛しもので、雨竜川の河口に多くの鵜が生息していたことから、このような名が付けられたといわれています。(雨竜町公式サイト「雨竜町の紹介」より)
雨竜川の河口に多くの鵜が生息していたとなっていますが、北海道ではカワウはほとんど生息していないらしいです。ウミウは北海道でも見られるらしいのですが、雨竜町は内陸なのでやはりカワウが昔はいたのでしょう。
北竜町
明治26年5月、千葉県の団体入植に源を発し、明治32年7月、雨竜町から行政区を分離し、戸長役場を置き、雨竜町の北に位置することから北竜町と称し、その発足をみた。(北竜町公式サイト「町の概要」より)
最近ではひまわりの町として有名になっています。
沼田町
沼田町の開拓は明治27年、富山県人沼田喜三郎翁が郷里から18戸の移住を図ったのがはじまりです。
大正3年、北竜村より分離し、上北竜村と称し、戸長役場を設置しました。大正7年、幌加内村を分割しました。大正8年、二級町村制を施行、村名を上北竜村とし、大正11年沼田村と改称、昭和22年に町制施行しました。(沼田町公式サイト「沼田町の紹介」より)
大正11年沼田村と改称とありますが、町開拓の功労者である沼田喜三郎の姓が由来であることは間違いないでしょう。
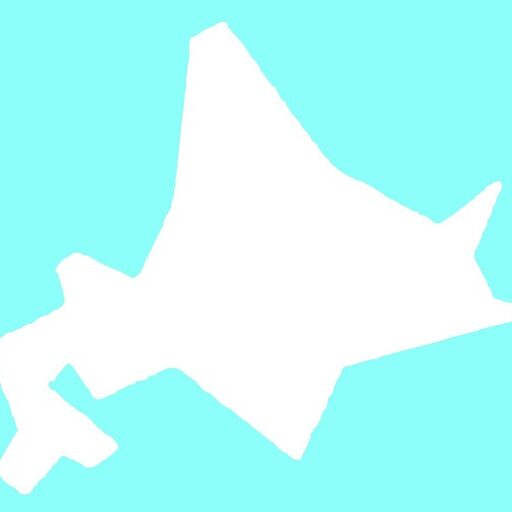
コメント